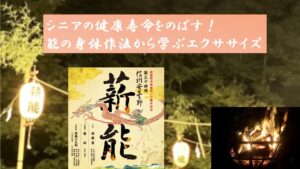腸を整えて健やかな秋を!『大腸を考える日』と梨の効能

9月26日の今日は『大腸を考える日』です。
数字の9が大腸の形に似ていることと、腸内細菌叢(腸内フローラ)が「2(フ)6(ロ)」と読める語呂合わせからきています。
この記念日は森永乳業株式会社が2019年に制定。人々の健康に対して大腸が果たす役割を、広く社会に知ってもらうことを目的にしています。
大腸の役割といえば健康に欠かせない働きを担っています。
・水分を吸収して便をつくる
・腸内細菌と共に栄養やビタミンを作り出す
・免疫細胞の多くが集まり体を守る
大腸を整えることは全身の元気をつくることにつながります。

◎腸の不調と現代病
大腸には約1,000種類、100兆個以上の腸内細菌が棲みつき、腸内細菌叢(腸内フローラ)を形成しています。
実は「善玉菌」は多ければ多いほど良いと思っていました。ところが腸内細菌の世界ではバランスがいちばんたいせつなのです。
腸内細菌は、善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割の比率が理想といわれています。
この割合がくずれると便秘や下痢・肌荒れ・疲れやすさなどの不調が出てきます。
もし善玉菌がすごく増えすぎてしまうと発酵が過剰になり、お腹の張りやガスが増え、下痢や軟便が続くことがあります。
さらに、小腸に入り込んでしまうと、小腸に大量のガスが発生してお腹の張り感が強く苦しく感じるSIBO(シーボ=小腸内細菌異常増殖症)とよばれる疾患も最近は注目されています。
ですので特定の菌を増やすのではなく、いろいろな菌が共存している状態をつくることが健康につながります。
それには、腸に良いといわれる発酵食品や食物繊維も摂り過ぎないことがとてもたいせつ。
睡眠不足やストレスも腸内細菌を乱します。
腸は「第二の脳」とも呼ばれて、心と体の健康に直結しています。
腸を整えて、秋の日々を健やかに過ごしていきましょう。

◎当院での腸ケア
東洋医学では、大腸は肺と表裏の関係にあります。
秋は乾燥しやすく、肺と大腸がともに影響を受けやすい季節で、呼吸と腸を同時に整えることが秋の養生にもつながります。
当院ではお腹の不調(便秘や下痢)に対して鍼灸治療を行っています。
・お腹を温めて腸の動きをサポート
・手足のツボで気血の巡りを改善
・心身のバランスを整え、腸にやさしいセルフケアのアドバイス
腸の不調でお悩みの方は、ぜひお気軽に当院にご相談ください。
 安曇野産『南水』
安曇野産『南水』
◎今が旬の梨と大腸の関係
今が旬の梨。
実は梨は大腸と肺の健康にぴったりな果物なのです。
梨は秋の乾燥から肺を守って、肺を潤し、熱を下げて、喉の乾燥や空咳、のどの炎症など喉の深い症状を改善してくれます。
冷え症や下痢気味の人は梨を煮ると咳や痰を鎮めてくれます。
また、カリウムの含有量が多く、ナトリウムを排出してくれるので、高血圧の予防にも効果的です。
そして、梨は果肉に点在する「石細胞(せきさいぼう)」と呼ばれる硬い細胞にセルロースなどの食物繊維があり、体内に吸収されず腸を通過して便通を促し、便秘解消が期待できます。
 ◎信州生まれの梨『南水』
◎信州生まれの梨『南水』
梨はこのように腸内環境を整える働きがあります。
9月のこの時期にはたくさんの梨が出回っています。
その梨の種類の中でここ信州生まれの梨が『南水』です。
梨の種類は50以上もあるそうですが、『南水』は「越後」と「新水」を掛け合わせてできた新しい品種。
南水は他の梨の種類より大玉で、日持ちがよくて常温で1か月、冷蔵で2~3か月もちます。
糖度が高くて酸味が少なくジューシーな甘みで、かむとシャキシャキとした歯ごたえのある食感です。
形がふっくらしていて、表面が滑らかで茶褐色、ズシリと重みのあるものがオススメです。
 ◎セルフケア教室情報
◎セルフケア教室情報
10月のセルフケア教室は25日(土)に開催予定です。今回は『晩秋の養生について』を開催予定です。詳細は『セルフケア教室情報』からご覧ください。