シニアの健康寿命をのばす! 能の身体作法から学ぶエクササイズ
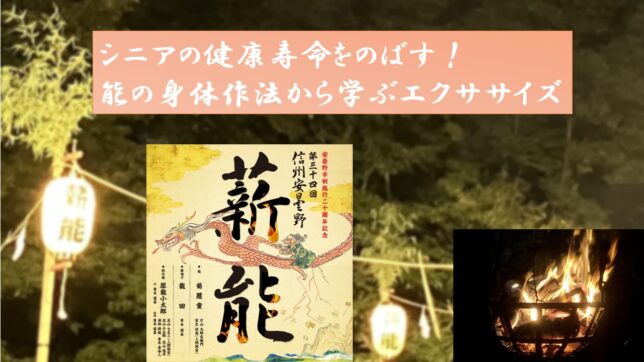
安曇野市にある当鍼灸院には、シニア世代のお客様が多く来院されます。
お客様が共通して気にされていることは「いつまでも元気に動ける体でいたい」という切なる願いです。
転倒や筋力低下は生活の質を下げ、『健康寿命』を縮めてしまいます。
そこで、その解決のヒントとしてお役に立つのが、日本の伝統芸能である「能」です。

◎『信州安曇野薪能』を鑑賞
先日、安曇野市明科龍門渕公園で開かれた『信州安曇野薪能』に行ってきました。
今年は安曇野市制施行20周年を記念して、安曇野の民話をもとにした能『犀龍小太郎』(さいりゅうこたろう)が上演されました。
私は最後列の席で観劇。その遠い席からでも伝わる、能楽師が面や重い衣装をつけながらも一言一句鮮明な言葉で腹の底から響くような発声ぶりと、ぶれない美しい立ち姿勢にただただ圧倒されていました。
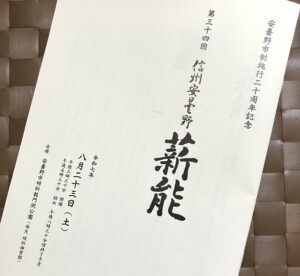
◎能との出会いから気づいた「姿勢のたいせつさ」
思い返せば、小学生のころにテレビで放映された古い映画を見たことが「能」というの世界を知っ薪能きっかけだったように思います。能楽師の世界を描いたその作品は『獅子の座』という映画でした。
その映画の記憶が少しはあったのかもしれないのですが、学生時代には伝統のある『能楽研究会』のサークルに入部。
短い在籍でしたが、そこで習ったのが能の基本動作のひとつである「すり足」でした。
かかとを上げずに、足の裏を床につけたまま、するようにして歩くのですが、上半身が動かないようゆっくり進む動作は思いのほか難しく、この体験は身体感覚というものを知るきっかけになりました。
その後リハビリの学校の授業で先生から「姿勢の良い職業は何か?」と突然質問されたことがありました。とっさに『能楽師』と私は答えのですが先生にとっては想定外の職業だったようです。
そのとき私自身は初めて、『能楽師=姿勢の良さ』というイメージを心に持ち続けていたのだと気づいたのです。 ◎能の身体作法はシニアの健康寿命を支える
◎能の身体作法はシニアの健康寿命を支える
能楽師の動きを健康目線で見直しみると
・腰を立てる姿勢:体幹を安定させ転倒防止に役立つ
・腹式呼吸と発声:呼吸筋を鍛えて声を明瞭になり誤嚥予防にも
・すり足歩行:足腰の筋肉を鍛え、バランス感覚を高める
・上半身を動かさずに歩く:姿勢保持力が高まり、腰痛や肩こりを防ぐ
・ゆっくりした動作:筋肉と脳を同時に刺激し認知症予防にもつながる
能の身体作法には、シニア世代に必要な「転ばない体」「疲れにくい姿勢」を支える要素が詰まっています。それを日常生活に取り入れることで健康寿命を支えてくれます。
 ◎能に学ぶ5つの転倒予防エクササイズ
◎能に学ぶ5つの転倒予防エクササイズ
では、この能の身体作法を生かした日常生活でもできるシニア向けのエクササイズを五つご紹介します。
①腰を安定させる(腹の座った姿勢)
椅子から立ち上がるとき、腰をすっと立て背筋を伸ばす。体幹が自然に鍛えられます。
②腹から声を出す(腹式呼吸と発声)
お腹に息をためるようにしてゆっくり吐きだす。挨拶や歌を「腹から声を出す」ことを意識して行うと呼吸筋トレーニングになります。
③すり足で歩く(転倒予防)
シニア世代のすり足は猫背になって足元ばかりを見て歩きが不安定になりがち。遠くを見据え胸を張るだけで背筋が伸びて姿勢が改善されます。ゆっくりとすり足歩きをすると足腰とバランス感覚が鍛えられ歩行が安定します。
④上半身を動かさずに下半身を使う(体幹トレーニング)
足が動いても頭や肩は揺らさないようにします。体の中心(おへそまわり)で姿勢を支えます。買い物袋を持つ時も背筋を伸ばす。テレビを見ながら座ってお腹を引き上げるなど意識するだけでも効果があります。
⑤ゆっくりていねいに動く(集中力と安心感)
あせらずゆっくりと落ち着いて動くことで、筋肉と能が同時に働き、安定した体づくりにつながります。
この5つを日常に取り入れることで、姿勢が整い、転びにくい、元気に動ける体づくりにつながります。
「健康寿命をのばしたい」「転倒予防や姿勢改善をしたい」と考えているシニアの方は、ぜひ日常に「能」の知恵を取り入れてみてください。

◎セルフケア教室情報い
セルフケア教室は、9月20日(土)です。テーマは『はじめてのお灸~よもぎからもぐさをつくろう~』です。詳細はセルフケア教室情報でご確認ください。


