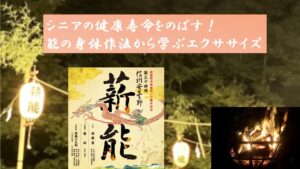夏に一粒 梅干しの力

暑い日が続いています。
7月22日~8月6日までの「大暑(たいしょ)」は、1年で最も暑い時期にあたります。
この時期、体がだるくなったり食欲が落ちたりしていませんか?
そんなときこそ昔ながらの梅干しの出番です。
今日7月30日は「梅干し」の日です。
「梅干し」の原型ともいえる保存食は中国から日本に伝わったとされています。
奈良~平安時代には薬として貴族の健康管理に、鎌倉~戦国時代には武士の保存食や常備食として用いられていました。
江戸時代には、一般家庭でも作られ「日の丸弁当(白ご飯+梅干し)」は庶民の定番でした。
梅干しが長く愛されてきた理由はおいしさだけでなく、さまざまな健康効果があるためです。

◎梅干しの効能
梅干の効能として知られているのは
① 疲労回復:クエン酸が豊富で、乳酸の分解を助けて疲れをとる効果。
② 食中毒予防:強い抗菌作用があり、お弁当やおにぎりに梅干しが入っているのは昔からの知恵。
③ 整腸作用:梅干しに含まれる有機酸(クエン酸など)が唾液の分泌を高め、胃腸を刺激して消化液の分泌を促して腸内環境を整え、便秘や下痢の症状を改善。
④ 血流改善・高血圧予防:毒素の排出を促し、血液をサラサラに保つ働き。
⑤ 美容・老化防止:抗酸化作用によって細胞の老化を予防。

◎東洋医学からみた梅干しの力
東洋医学では、梅干しはこんなふうにとらえられています。
・気を巡らせ内臓の働きを整える
梅の酸味は「肝」に作用してストレスによるイライラや疲労感を和らげます。
・胃腸を助けて消化力をアップ
「脾・胃」を助けて、夏のだるさや食欲不振をサポートします。
・汗を引き締め、体液を守る
酸味には収斂(しゅうれん)作用として気や津液が体から漏れ出さないようにする働きがあり、汗のかき過ぎを抑えて体を潤す働きがあります。
梅干しには、夏の疲れやすい体を内側から穏やかに整えてくれる働きがあるのです。

◎女性にうれしい梅干しの効果
梅干しは女性の不調にもやさしく寄り添ってくれるすぐれものです!
・冷え症:血流を良くして冷えの改善を図ります。
・PMS症状:生理前のいらいらやむくみに、クエン酸のデットクス作用が、気の滞りや水の滞りの改善をサポートしてくれます。
・美容・アンチエイジング:抗酸化作用で肌のくすみや老化予防効果があります。
(梅干しローションの作り方)
角質化したかさかさ肌やシミなど肌の改善に効果。
① 梅干しを5~6個用意。2~3日温水につけて塩抜きする。
② ざるに上げ、水を切ってコップ1杯の日本酒に1週間ほど漬け込む。
③ 梅干しを取り出して、液をカーゼでこしてビンに入れ冷蔵庫で保存。
④ 入浴後に肌荒れの部分にマッサージするようにやさしくすり込む。

◎大暑の時期にヘルシーな梅干しの食べ方
この大暑の時期は汗をかいて、ミネラル不足、食欲不振、だるさなど不調になりがちです。
そんなときに梅干しを使ったオススメの食べ方をご紹介します。
・梅しそ冷やし茶漬け:梅干しと青しそ(大葉)を刻んでごはんにのせ、冷たい緑茶を注ぐだけ。さっぱりとして食べやすく、食欲がなくてもスルスルと口に入ります。夏バテで食欲がない日にもOK。
・梅干しと鶏の胸肉のさっぱり炒め:刻んだ梅干しと鶏の胸肉を焼いて炒めるだけ。クエン酸×高たんぱく質で元気を回復!
・梅昆布水:梅干し1個+昆布数cmを水に入れて一晩置くだけ。
梅干しは、小さな粒に自然の力と先人の知恵がぎゅっとつまった保存食品です。
毎日でなくても、体がだるいときや心が疲れているとき、食欲がないとき、そんなときに、そっと梅干しを一粒。この小さな一粒が、体と心もそっとやさしく整えてくれます。

◎セルフケア教室情報
8月のセルフケア教室は『秋バテ予防のセルフケア』をテーマに8月24日(日)に行います。詳細はセルケア教室情報からご覧ください。